メタボリックシンドロームについて
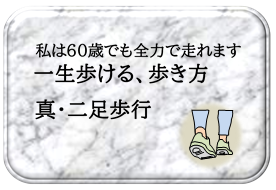
メタボリックシンドロームの人口は、2024年に実施された厚生労働省の調査によると、患者数は成人で約2700万人(予備軍も含める)、40歳以上では、1960万人とも言われています。
世界的規模で見ると、成人で8億8000万人、子どもが1億5900万人が肥満人口として報告されています。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満、さらに高血圧、高血糖、脂質異常症、これらのうち2つ以上に該当する場合を指します。
特に内臓脂肪型肥満は男性に多くみられます。そのためメタボリックと強く疑われるのは男性27.5%、女性11.9%と男性が2倍以上と多いとされます。
肥満がなぜ危険なのか?については、脂肪細胞から出される「メッセージ物質」が異常を引き起こし、高血圧、高血糖を引き起こし、ひいては心疾患、脳血管疾患を引き起こす危険性があるからだという研究があります。
メタボリックシンドロームの改善方法とは主に、「食事療法」「運動療法」の二つです。
どちらも生活習慣病を解決するには不可欠なものです。
「運動療法」とは、ウォーキングやジョギング、水泳、体操などを行いなさいというもので、一週間当たりの運動量が多いほど、内臓脂肪の減少がしやすいの報告があります。考えてみれば当然のことですね。とくに中高年は運動不足に陥りがちです、仕事などで「脳を使うと」疲れを感じます。しかし、疲れを感じるからカロリーを消費しているとは限りません。自分で思っているより、運動量は足りていないのが実情です。
「食事療法」とは、適切なエネルギー摂取をしたうえで、運動をしてエネルギーの消費量を増やすことです。その工夫としていくつかの項目が挙げられています。
- 食塩は10/日g以下に控える。
- こんにゃくやキノコなどの食物繊維を多くとる。
- グリセミックインデックス値の低い食べ物を食べるようにする。
- 甘いジュースやお菓子を控える。
- よく噛んで食べ、腹7~8分目で抑える。
- 緑黄色野菜を積極的にとる。
- 間食や夜食をせずに決まった時間に食事する。
- アルコールを飲み過ぎない。
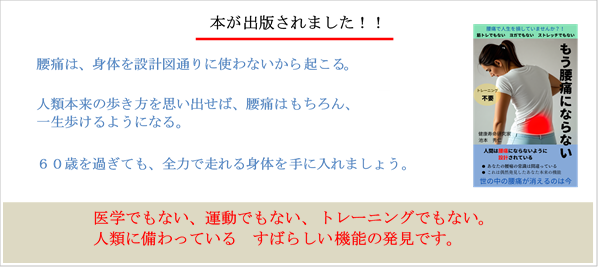
一日3食が、栄養過多の始まり!
メタボリックシンドロームの対策として「食事療法」が挙げられますが、決まった時間に食事をとるというと1日3食きっちりとると思われる方も多いと思います。
特に朝食は絶対抜かないという定説まであるようです。
しかし、ここで1日3食は本当に正しいのか?と疑問が浮かびます。
現代は、特に日本においてはカロリーの過剰摂取が問題になっています。なぜ過剰摂取が起こるのか?もちろん、なんでも食べたいものが手に入る環境が大きいのですが、脳が覚える習慣がもっとも危険と言えます。
諸説ありますが、1日3食が始まったのは江戸中期ごろ、さらに昭和に入ってそれが定着していったということです。それは結構最近のことです。
朝食が大事という説も、「朝食を採らないと頭が回らないから」というものですが、それも医学的に確かな根拠があるというよりは、現代の学校や仕事上、朝から働きなさいというメッセージ性の方が強うように思われます。
もともと、一日3食とることで摂取カロリーは多くなります。そこへそれ以外の時間に間食するなどが加わればさらに余分なカロリーを採ることになります。
一日のサイクルを見てみても「1日24時間を3で割ってみれば8時間に一回となります。」
睡眠時間を8時間とすると、1日3回食するためには6時間おきに食事することになります。
一方、食べたものが消化される時間は、炭水化物で2~3時間、タンパク質で4~5時間、脂肪などは7~8時間はかかります。
十分に消化が終わる前に、もう次の食事が始まってしまいます。
これではサイクルが早すぎるとは思いませんか?
ここでズームアウトしてみましょう。
本来、動物はお腹がすいた時に食べる。これが基本です。
現に野生動物は目の前に食べ物があっても、お腹いっぱいになった時点で食べるのを止めてしまいます。そしてまた空腹になるまでは何も食べません。
現代人のように、いつでも何でも食べられる。目の前にあるものは全部食べる。お腹がすいていなくても手持無沙汰や休憩の時に何かを食べる。などということはありません。
そこには人間の機能も関係しているようです。世界中の生物の中でこれ程広い地域に分布している生物はいません。人間の身体は他の霊長類、例えばチンパンジーなどよりも脂肪を蓄えれるようになっています。ちなみにチンパンジーの体脂肪率は5%~7%しかありません。人間は20%程度もあります。
つまり、長距離移動、長時間移動できるために、エネルギーを蓄えれるようにできているわけです。
1日3食が健康にいいとされることで、脳の習慣としてそれが刷り込まれれば、もともとエネルギーをため込むことができる人間は、とうぜんエネルギーをため込もうとします。
そこには、「本当に空腹かどうか」とか「これからエネルギーを使うから」とういことは関係ないのです。
食事は、空腹を感じてから、あるいは12時間は何も食べないのが良い。
本来ならば、動物の構造的には「本当に空腹になるまで何も食べない」ことが体には合っていると言えます。しかし、現代の生活から食事を好きな時に採るのは時間的に言ってもあまり現実的ではありません。
そこで、一日24時間のうち、「12時間は何も食べない時間を作る。」これを実践するといいと思われます。
さらに、12時間の中で、食事をするのは1回~2回、もちろん、1回が望ましいと思いますが、2回でも大丈夫です。ただし間食はなるだけ避ける。
例えば
- 夕食が20時に食べ終わったなら、そこから12時間後の翌8時までは何も食べない。
- 夕食が18時にため終わったなら、そこから12時間後の翌6時までは何も食べない。
一日一食ならこれだけでOKです。
もしも一日2食なら、どこかでもう1食を加える。
簡単に言うと「一日1回は胃腸を空の状態にする」ことです。
このサイクルなら太ることなく生活できるようになります。(ただし、間食はしない)
これだけ守れば、後は「メタボリックシンドロームの健康療法」をちょっと意識するだけです。(野菜を食べるとか、お酒を控えるとか)
運動療法については、メタボリックシンドロームの典型はお腹が出て後ろ重心になっているので、重たい上半身を下半身に乗せて運んでいる歩き方になっています。

この歩き方は、腰にも大きな負担を掛けている他、長距離を歩くことが身体に大きな負担となり長く歩けません。また走ることもできないでしょう。
このような状態では「運動療法」はうまくいきません。
健康維持に大切なのは歩くこと、そして本来、歩いているときに身体は体調を調節しているのです。
その調整ができていないのでは、せっかく歩いても身体を壊すことになりかねません。
詳しい「本来の人類の歩き方」については下記の著書に詳しく書いています。
本来の歩き方を手に入れて、健康な毎日をお送りください。
著書紹介

「もう腰痛にならない」は腰痛にならないための著書です。
内容は、ズバリ「歩き方を元に戻す」ことです。
人類本来の歩き方をすれば「腰痛にならない」だけではなく「生涯、自分の足で歩けるように設計されている」ということが書かれています。
現在の高齢者の歩いている姿は、ポチポチとトボトボと歩いています。それは、青信号の間に横断歩道を渡り切れないほど、そうでなくても50歳も過ぎれば「昔のように全力で走ることができる」という人が何人いるでしょうか?
動物の世界をちょっと想像してみてください。
そんな状態ではとても自然界では生きていけません。他の動物に捕食されることは当然として、自分で食べ物を探すことも獲物を捕まえることすらできません。
人類も元々はそのような過酷な環境で生きてきました。そんな人類の体が年を取ると歩くことすらままならない。走ることもできない。そのような設計なはずはありません。
ちゃんと人類の足腰も「生涯歩ける。生涯走れる」ように設計されています。
私はその歩き方を本来の二足歩行という意味で「真・二足歩行」と呼んでいます。
当然、あなたの足腰もそのような作りになっています。
「真・二足歩行」で、私も60歳を過ぎても元気に走り回れます。
私の真似をしてみましょう。
これからの超高齢化社会、自分の足で歩き、健やかな生涯を送りましょう。
一生 自分の足で歩きたいなら >>>Amazon



コメント